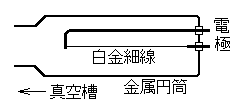 構造と原理
構造と原理「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊
1998.11.26
keywords: pirani gauge
低温の気体分子が高温の固体に衝突すると、固体から熱を奪います。奪った熱量から圧力を求める真空計を総称して熱伝導真空計と言い、中真空領域の圧力測定に広く用いられています。市販されている熱伝導真空計には、ピラニ真空計と熱電対真空計とがあり、このページでは前者について、次ページで後者について説明します。
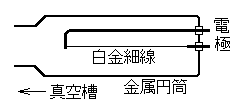 構造と原理
構造と原理
測定子の一般的な構造は、右図に示すように金属円筒の内部に白金細線が張られ、その両端が電極に繋がっているだけで、極めて単純です。
電極を通じて細線に電流を流すと細線は自身の抵抗によって加熱されます。気体分子が細線に衝突することによって、輻射によって、あるいは電極への固体熱伝導によってこの熱は細線から奪われます。単位時間当たりにそれぞれの現象によって奪われる熱量を順に Qg、Qr、Qs とすると、定常状態では
Q = I2R = Qg + Qr + Qs (1)
が成り立ちます。ここで Q は細線の単位時間当たりの発熱量で、R は細線の抵抗、I は細線に流れる電流です。
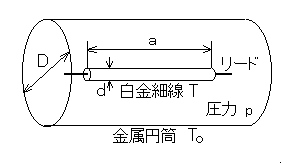 気体の平均自由行程λ が細線の直径 d よりも充分大きいとき、Qg
は自由分子の熱伝導率Λ を用いて、
気体の平均自由行程λ が細線の直径 d よりも充分大きいとき、Qg
は自由分子の熱伝導率Λ を用いて、
Qg = αΛπda(T−T0)p (2)
と表されます。右図に示すように、T と T0 はそれぞれ、細線と金属円筒の温度(注1)、p は気体の圧力、a は細線の長さで、α は適応係数です。この式は付録A-4で説明している(9)式の両辺に、細線の表面積πda を乗じたものですが、熱量と圧力が比例していることが判ります。
残りの Qs と Qr については、それぞれ次のように表されます。
Qs = Sκ(T−T0)/L (3) Qr = πdaσε(T4−T04) (4)
(3)式は電極(リード)への固体熱伝導を表しており、S は細線断面積(=πd2/4)、κ は固体の熱伝導率、L は代表長さです。(4)式は輻射による放熱量を表し、σ と ε は、それぞれステファン・ボルツマン定数と固体の輻射率です(注2)。ここで、T と T0 が一定になるように制御すると、(3)式と(4)式より Qs と Qr は定数となることがわかります。そこで、両者の和を I02R で置き換えると、(1)式は次のように書き換えられます。
I2R = Ap + I02R (5)
A = αΛπda(T−T0) (6)
I0 は、圧力が 0 の場合に細線に流れる電流、つまり固体熱伝導と輻射によって逃げる熱量を供給するための電流を表しています。また、A は(2)式において圧力に依存しない項をまとめた定数です。
細線の抵抗 R、ベース電流 I0(注3)、および定数 A が既知であれば、細線に流れる電流 I から(5)式を用いて圧力 p を求めることができます。これがピラニ真空計の測定原理です。なお、 I0 は測定子の形状や材質に依存しますが、A はこれらの他に気体の種類にも依存します。
ピラニ真空計では細線の温度 T を一定に保つために、細線に流す電流 I を制御しなければなりません。通常は、金属の抵抗値が温度に対してほぼ単調に増加するという性質を利用し、抵抗値が一定になるように制御します。市販品では交流ブリッジ回路を用いているようですが、直流ブリッジ回路でも充分役に立ちますし、自作も簡単です。回路例は付録B-1をご覧下さい。
圧力測定範囲
(2)式は、気体の平均自由行程 λ が細線の直径 d よりも充分大きい場合にしか成り立ちません。例えば、d = 25μm としますと、λ = 10d となる窒素ガスの圧力は 27Pa (0.2Torr) です。他の式を用いて換算するともう一桁高い圧力を測定することができますが、精度は若干悪くなります。詳しくは付録B-2をご覧下さい。
圧力の下限値は、通常は I0 、つまり固体熱伝導と輻射による放熱量によって決まります。実測によれば、ある市販測定子の I0 は 10mAでした。従って、窒素ガスを測定した結果 11mA という電流値を得、その差1mA が有意だと考えても、圧力は 0.5Pa (4mTorr) であり、これ以下の圧力を測定することはできません(換算については付録B-2をご覧下さい)。
ここで、ベース電流 I0 について簡単に考察します。(3)式や(4)式から Qs や Qr の値を計算によって求めると、実験に依らなくても I0の値を知ることができます。しかし(注2)で述べたように計算は困難なため、実測に頼らざるを得ません。具体的には、測定子を真空系に接続して圧力を下げて行き、細線に流れる電流が圧力に依存しなくなるときの値が I0 になります。上に述べた測定子では、 0.1Pa 以下で常に 10mA を示しました。 従って、Qs + Qr = 2mW です。(4)式において輻射率εを 0.2 と仮定しますと、Qr はほぼ2mW となり、輻射の方が固体熱伝導よりも放熱に寄与していると推測されます。
より低い圧力を測定する方法はいくつか考案されています。I0 をより正確に決定できれば有効数字は増えますから、低圧まで測定することが可能です。このためには周囲の温度 T0 を一定に保つ必要があります。しかし、同じ努力(?)をするなら、恒温槽に入った隔膜真空計を用いた方が精度よく全圧を計ることができます。周囲の温度を一定に保たなくても(ただし空調でできる程度には一定に保って)、同一の測定子を2つ準備し、片方は高真空に封じ、もう片方は測定に用いる方法があります。I0がキャンセルされるため、1桁程度低い圧力まで測定できるそうです。凝った方法としては、測定子を液体窒素で冷却し、細線の設定温度を下げれば、更に低い圧力まで測定することが可能です。周囲温度が一定になることと、輻射熱(絶対温度の4乗に比例)が極端に減って、I0 が小さくなるからです。ただし、あまり実用的とは言えません。
特徴と用途
測定範囲が 0.5〜 300Pa であることから、中真空領域の圧力モニタとしてよく用いられます。大気圧中で動作させても断線しないこと、ガイスラー管よりもはるかに定量性に優れ、電気信号も取り出せることなどから、高真空〜超高真空排気系の粗引きラインや、高真空ポンプの背圧ラインに多用されています。ただし、気体の種類や組成によって表示値が異なりますので、絶対圧力を測定するためには事前に充分較正しておかねばなりません。この点においては隔膜真空計の方が優っています。
競合する真空計としては、同じように熱伝導を利用した熱電対真空計が挙げられます。概して言えば、ピラニ真空計の方が若干測定範囲が広く、測定子が丈夫で安価である反面、測定器は高価のようです。
接続方法
メーカーや型番によって異なりますが、非測定系(真空側)へは、ゲージポートかクランプ継手を介して接続するものが多いようです。
超高真空用のコンフラットフランジが接続された市販品は無く、また本体が真鍮製であるためにフランジが溶接できないようです。もともと測定範囲が中真空領域ですので、超高真空中で使用することはあまり無いのですが、超高真空槽に気体を外部から導入する場合に、モニタとして利用できないのは残念です(注4)。
(注1) 金属円筒の温度と測定子内の気体の温度は等しいと仮定している。 (注2) (3)式における L の定義はあいまいであるし、(4)式は無限空間に対しての輻射放熱式であるから、これらの式から固体伝導熱や輻射熱を正確に求めることはできない。ここでは、温度 T が一定の場合には固体伝導熱も輻射熱も一定になることを式の形から説明するために用いた。 (注3) トランジスタ特性を記述する用語と紛らわしいが、ここでは圧力に依らず常に流れる電流という意味で用いている。 (注4) 一般的にはピエゾバルブと高真空計を組み合わせ、真空槽内の圧力を一定に保つように気体の流量を制御するため、ピラニ真空計が必要なのは特殊な場合である。
以上
このページは、高木郁二が担当している京都大学工学部物理工学科の講義・実験を補う資料として作成したものです。ご意見・お問い合わせはこちらまでお願いします。