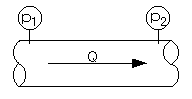 コンダクタンスとは?
コンダクタンスとは?「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊
1999.3.18 2001.12.13 rev.1
keywords: conductance, pipe, molecular flow, viscous flow, turbulent flow, Poiseuille flow, Knudsen number
概要
導管(パイプ)の中に水などの流体が流れているとき、その流れ易さを表す係数をコンダクタンスと言います。ここでは理論的な考察には立ち入らず、充分長い円形直管におけるコンダクタンスが、どのように表されるのかについて紹介します。短い管や断面が円形で無い管などの場合については、次ページで説明します。
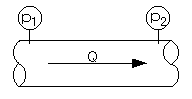 コンダクタンスとは?
コンダクタンスとは?
右図のように、パイプの中を流体が流れている状態を考えます。流れには抵抗が生じますから、上流側(左側)の圧力は高く、下流側(右側)の圧力は低くなります。言い方を少し変えると、例えば水道の蛇口を流れの根元と考えると、蛇口から遠ざかるほど圧力は低くなる、ということになります。図に示すように、ある2つの位置での圧力をそれぞれ、p1、p2 とすると、質量流量 Q が圧力差 Δp = p1 - p2 に比例すると仮定したときの比例定数をコンダクタンスと言い、一般には記号 C で表します。式で書くと次のようになります。
Q = C・Δp (1)
乱流と層流
コンダクタンスは流れの状態に依存します。あまり表現は適切ではありませんが、渦を巻くような濁流と、淀んだゆったりとした流れとでは、コンダクタンスは異なっています。流体の分野では、流れの状態を表す指標として、レイノルズ数 Re がよく用いられます。
Re = Dvρ/η (2)
ここに、Dは管の内直径、vは流速、ρは流体の密度、ηは粘性係数です。一般には、
Re < 1200 … 層流 Re > 2200 … 乱流
として、流れが速い場合には乱流、遅い場合には層流と分類されています。
ここで、(2)式を少し変形して、真空の分野で使いやすい形にしてみます。気体の流量Qを、体積×圧力/時間と表すと、Q = pvπD2/4 となります。また、密度は ρ = pM/RT (Mは気体の分子量)より、
Re = 4MQ/πηDRT (3)
となります。例えば常温の空気では、
Re = 0.82Q/D (4)
となります(注1)。ただし、Q と D の単位はそれぞれ、Pam3/s と m です。直径2.5cmのパイプを通して排気する場合、Q > 67 Pam3/s で乱流となります。排気速度 S が 150L/min (= 0.0025 m3/s) のポンプを仮定すると、Q = Spより p > 27 kPa 、つまり大気圧の1/4以上の圧力領域では乱流です。また、同様の条件下では、p < 14 kPa で層流になります。
上の計算例によると、真空槽を大気圧から排気し始めてから、ほんの暫くの間は乱流ですが、それ以降は層流になります。このように、「真空」においては乱流はあまり生ぜず、大抵の場合は以下に述べるような層流(粘性流)と分子流を考慮すれば充分です。
粘性流と分子流
気体の平均自由行程λが管内径Dよりも充分小さい場合には、粘性がコンダクタンスに関わりそうだということは、想像がつくと思います。逆に、λがDよりも充分大きい場合には、気体分子は管の内壁に衝突するばかりで、他の気体分子とはほとんど衝突しません。このような状況下では、分子間の相互作用は無く、一般的な粘性という概念は成り立ちません。従って、粘性が支配的である流れ(粘性流)と、分子と壁との衝突が支配する流れ(分子流)とを分けて考える必要があります。なお、粘性流は層流とほとんど同じ意味ですが、分子流という語と対比させて用いられることが多いようです。
上記の説明をまとめて示すために、クヌーセン数 Kn という無次元数を、
Kn = λ/D (5)
と定義します。すると、
Kn < 0.01 、 Re < 1200 … 粘性流 Kn > 1 … 分子流 0.01 < Kn < 1 … 中間流
と表されます。例えば常温の空気の場合、λ = 0.68/p [cm] (p: Pa) と表されるので、D = 2.5 cm の管では、p < 0.27 Pa (2 mTorr) で分子流、p > 27 Pa (0.2 Torr) で粘性流になります。
粘性流におけるコンダクタンス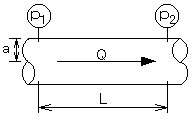
右図のように、円形の管内を気体が流れている場合、流量 Q (注2)はポアズイユの法則によって次のように表されます。
Q = (πa4p/8η)(p1 - p2)/L (6)
コンダクタンス C は(1)式と(6)式を比較することにより、
C = (πa4p/8η)/L (7)
であることが判ります。ここで、a はパイプの半径、pは気体の平均圧力 (p1+p2)/2、η は粘性係数、L は2地点間の長さです。また、流量 Q は単位時間に通過する気体の体積と圧力の積で表した質量流量です。蛇足ですが、平均流速 v は Q/πa2p です。 常温の空気ではη = 18.1 μPa.s より、
C = 0.0217a4p/L [m3/s] (8)
と表されます。ただし、p の単位は Pa、a と L の単位は cm です。例えば p = 1 kPa、a = 1.25 cm、L = 30 cm の場合、C = 1.8 m3/s になります。
粘性流におけるコンダクタンスの特徴は、(8)式を見るとよく判ります。粘性係数は圧力にほとんど依存しないので、近似的に定数と見なすことができ、式中には変数として含まれません。従って、管の半径(直径)の4乗に比例することと、平均圧力に比例することが特徴と言えます。
分子流におけるコンダクタンス
粘性流の場合と同様に結果だけを示すと、
C = (2πa3v/3)/L (9)
となります。ここで v は気体分子の平均速さです。v = (8kT/πm)1/2 より、分子量 M の常温の気体では、
C = 0.523a3/(M1/2L) [m3/s] (10)
と表されます。ただし、a と L の単位は cm です。更に、気体を空気に限定すると、次のような覚えやすい式になります。
C = a3/L [Liter/s] (11)
ただし、a と L の単位は mm であることに注意して下さい。また、C の単位は Liter/s です。例えば、a = 12.5 mm、L = 300 mm の場合、C = 6.5 Liter/s = 0.0065 m3/s になります。
(10)式または(11)式によると、分子流におけるコンダクタンスは、半径(直径)の3乗に比例することが判ります。粘性流の場合と比較すると、圧力の項が含まれない点が最も異なっており、コンダクタンスは圧力に依存しないことが分子流の特徴です。
中間領域におけるコンダクタンス
粘性流におけるコンダクタンス(7)式や、分子流におけるコンダクタンス(9)式は解析的に求められた式ですが、中間領域でのコンダクタンスを解析的に求めることはできません。そこで、一般には Knudsen が提案した以下の近似式が用いられます。
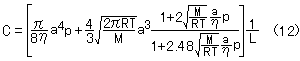
L が括弧の外に出ていることに注意すれば、括弧内第1項は粘性流におけるコンダクタンス、第2項の前項は分子流におけるコンダクタンスの式です。従って、この式は粘性流と分子流それぞれのコンダクタンスの式をなめらかにつなぐような形になっています。なお、常温の空気では、
C = [0.0217a4p + 0.097a3(1+3.813ap)/(1+4.729ap)]/L [m3/s] (13)
となります。ただし、a と L の単位は cm、p の単位は Pa です。
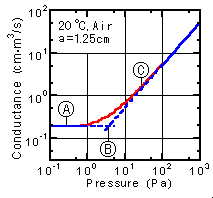 常温の空気が a = 1.25 cm の円形導管内を流れている場合のコンダクタンスを、圧力領域に応じて(8)式、(10)式及び(13)式を用いて計算し、右図に示しました。縦軸は単位長さ(1cm)当たりのコンダクタンスであり、例えば
30cm の導管の場合には、縦軸の値を 30 で割った値がコンダクタンスになります。
常温の空気が a = 1.25 cm の円形導管内を流れている場合のコンダクタンスを、圧力領域に応じて(8)式、(10)式及び(13)式を用いて計算し、右図に示しました。縦軸は単位長さ(1cm)当たりのコンダクタンスであり、例えば
30cm の導管の場合には、縦軸の値を 30 で割った値がコンダクタンスになります。
図中、A と C の点は、それぞれ、Kn = 1 と Kn = 0.01 に対応する圧力を示しています。赤い線で示した中間領域でのコンダクタンスは、A から C の圧力範囲とほぼ一致しており、近似式が有用であることが判ります。
B点は、(8)式と(10)式を外挿した交点です。(12)式や(13)式のような複雑な式を用いず、単に流れを分子流と粘性流に2分して考える場合には、この圧力 pbを境界とするのがよいでしょう。一般的な式としては、(7)式と(9)式より、
pb = 16vη/3a (14)
となり、常温の空気では、(8)式と(10)式より、
pb = 4.47/a [Pa] (15)
となります。ただし、a の単位は cm です。右上図の例(a = 1.25 cm)では pb = 3.6 Pa です。
(注1) 粘性係数は圧力に依存しないと考え、常温常圧での値 18.1 μPa.s を用いた。 (注2) 管の中心からの距離によって流速が異なるので、Qは、管の断面積について流速を積分した値である。
以上
(rev.1) 図中の記号を本文と対応(大文字のPと小文字のp)、クヌーセン数 K が他のパラメータと紛らわしいため、Kn と表記を改めた。
このページは、高木郁二が担当している京都大学工学部物理工学科の講義・実験を補う資料として作成したものです。ご意見・お問い合わせはこちらまでお願いします。