 「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊
「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊 「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊
「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊
1999.02.16
keywords: quadrupole mass analyzer, residual gas analyzer, mass filter
2種類以上の気体が混合された状態において、それぞれの気体が示す圧力を分圧と言います。この分圧を測定するのが質量分析計に代表される分圧計です。質量分析計が全て分圧計として機能するわけではありませんが、真空の分野ではほぼ同じ意味で用いられています。質量分析計は、残留ガス分析計やマスフィルタなどとも呼ばれます。
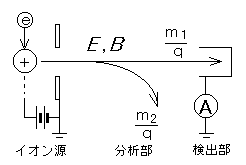 原理と種類
原理と種類
右図に示すように、質量分析計はイオン源、分析部および検出部の3つの要素から構成されています。もし分析部が無ければ、前項で述べた電離真空計と良く似ていることが判るでしょう。電離真空計ではグリッドの近くで分子を電離し(イオン源)、生成されたイオンをコレクタで受けますが(検出部)、この間には何もないために、イオンは全てコレクタに捕集されます。一方、質量分析計では分析部を設け、電場や磁場を用いて特定の質量電荷比(m/q) を持つイオンのみを通過させるようになっています。イオン源の種類にも依りますが、通常は1価のイオンが生成されますので、q = e (素電荷)です。従って、分析部では特定の質量を持つイオンを選別していると思ってもよいでしょう。なお、図では m1/q のイオンが直進していますが、実際には電場や磁場によって軌道を曲げられます。
例えば窒素分子の質量は28ですが、一酸化炭素分子の質量も28です。質量分析計では質量を分離するだけですから、窒素分子と一酸化炭素分子を区別することはできません(注1)。残留ガス分析計という呼称から、その機能を誤解しないように注意すべきです。
分析部の形式はいくつか開発されてきましたが、現在では磁場偏向型(磁気セクター型)、オメガトロン及び四重極型の3つが使用されているようです。この中で四重極型が最も多く用いられていると思われるため、次節でやや詳しく扱うこととし、ここでは前二者について簡単に説明しておきます。なお、この他に飛行時間分析型(TOF)も充分実用に供されている優れた分析方法ですが、一般の残留ガス分析には用いられていないため、省略します。
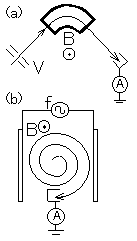 磁場偏向型は、イオンが磁場中でローレンツ力を受けて軌道を曲げられる場合に、曲げられる程度(回転半径)が質量電荷比に依存することを利用しています。右図(a)では偏向角が90度のように描いていますが、この他に60度や180度などもあります。左側で生成されたイオンは電圧
V で加速され、扇形の部分に紙面に垂直にかけられた磁場 B で軌道を曲げられます。右側にはコレクタ(検出部)があり、扇形の回転半径に一致するように曲げられたイオンのみが検出されるようになっています。導出は省略しますが、遠心力とローレンツ力の釣り合いより、回転半径
r は、
磁場偏向型は、イオンが磁場中でローレンツ力を受けて軌道を曲げられる場合に、曲げられる程度(回転半径)が質量電荷比に依存することを利用しています。右図(a)では偏向角が90度のように描いていますが、この他に60度や180度などもあります。左側で生成されたイオンは電圧
V で加速され、扇形の部分に紙面に垂直にかけられた磁場 B で軌道を曲げられます。右側にはコレクタ(検出部)があり、扇形の回転半径に一致するように曲げられたイオンのみが検出されるようになっています。導出は省略しますが、遠心力とローレンツ力の釣り合いより、回転半径
r は、
r = (2mV/q)1/2/B (1)
と表されます。通常、磁場は永久磁石から供給されますので B の値は一定です。従って、特定の m (正確には m/q) を選別するには式(1)を満たすような V の値に設定すればよいことが判ります。
磁場偏向型分析計には、磁場にイオンの収束作用があることや、数cm の回転半径でも残留ガスの分析には十分な分解能が得られるという特徴があります。一方、外部磁場を必要とするので、測定子全体としては大型になりがちであることや、質量の小さいイオンを分析するためには高い加速電圧もしくは磁場が必要であること、イオンのエネルギーを揃えなければ分解能が悪くなること(注2)などの欠点があります。
オメガトロンは、右上図(b)に示すように、交流(高周波)電場とそれに直交する磁場を印加し、特定の質量電荷比を持つイオンをサイクロトロン運動させて選別します。磁場偏向型と同じように考えると、イオンが円運動する角速度 ω は qB/m と表され、磁場の強さ B が一定であれば、ω は質量電荷比 m/q のみと関係づけられます。ω を周波数 f (ω = 2πf) で表したとき、この周波数をサイクロトロン周波数と言います。 f と交流の周波数を一致させると、m/q のイオンが円運動を半周する度に電場の向きが入れ替わり、加速され続けます。回転半径 r は mv/qB と表されますので、イオンの速さ v と共に r は増加することになり、図に示したような渦巻き状の軌道を描きます。このイオンは軌道上に置いたコレクタで捕集します。イオンは、電極で囲まれた空間の中心に、紙面に垂直な方向から電子ビームを照射することによって生成します。
イオンの軌道の最大半径、つまりイオン発生部からコレクタまでの距離が1cm であっても、軽い分子なら選別することが可能であるため、分析計を小さくすることが可能です。筆者が一度見たオメガトロンは、ガラス製の外囲器内に収められており、その大きさはB-Aゲージほどでした。しかし、磁場偏向型分析計と同様に外部磁場を必要とするため、周囲に大きな磁石が配置されていました。この欠点のため、現在ではあまり用いられていないようです。ただし、水素などの極く軽い分子のみを検出する場合には小さい磁石でもよい筈ですから、目的によってはメリットがあるかもしれません。
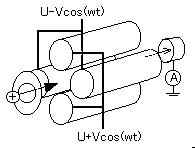 四重極質量分析計
四重極質量分析計
四重極質量分析計はその頭文字から QMA と呼ばれたり、四極マスフィルタと呼ばれたりしています。右図に示すように、分析部は4本の電極であり、Uという直流電圧と ±Vcos(wt) という交流を併せて印加しています。図では左側がイオン源であり、電極に囲まれた空間を通り抜けたイオンを右側のコレクタ(検出部)で捕集します。
このような簡単な構成でイオンを選別することができるのは、電極に交流を加えていることと、電極を4本にして2次元の電場を形成しているためです。以下では図を用いて直感的に判るように説明することを試みます。数学的な取扱は真空に関連する教科書を参照して下さい。
右下図では、電場をシーソーのような傾斜で表しています。(a)のように電極を2本用いて交流を印加した場合、左側の電圧が上がるとイオンは右向きに力を受け、下がると左向きに力を受けます。重力と異なる点は、力が質量に無関係であることで(注3)、このために加速度(= 力/質量) は軽いイオンほど大きくなります。従って、軽いイオンほど勢いがつきやすく、シーソーの周期が長い(交流の周波数が低い)と勢い余ってシーソーからはみ出してしまいます。これは一種の質量分析ですが、ある質量以上の重いイオンはどれもはみ出さないため、特定のイオンのみを選別することはできません。
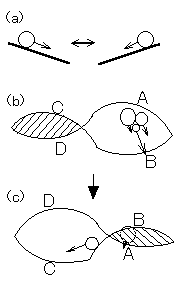 軽いイオンも重いイオンもシーソーから落とし、目的のイオンだけ残すためには、右図(b)、(c)に示すように、電極を4本用いて馬の鞍のような電場を交互に波打たせるようにします。図では
A〜D が電極であり、鞍の裏側はハッチで表しています。図(b)では AとCが正、BとDが負(注4)になっています。
軽いイオンも重いイオンもシーソーから落とし、目的のイオンだけ残すためには、右図(b)、(c)に示すように、電極を4本用いて馬の鞍のような電場を交互に波打たせるようにします。図では
A〜D が電極であり、鞍の裏側はハッチで表しています。図(b)では AとCが正、BとDが負(注4)になっています。
先ず AとCとの間に正イオンがあると考えます。質量の大小によらず、どのイオンも電極Bに引き寄せられますが、上で述べたように軽いイオンほど加速度が大きく、早く移動します。時間が少し経過して図(c)のように、つまり BとDが正でAとCが負になったとき、軽いイオンは勢い余って電極Bに捕集されてしまいます。重いイオンはAとBとの間に取り残され、Aの方向に力を受けます。そして、適当な質量のイオンだけが電極Bによる電場の山を越えてBとCの間に進みます。さらに少し時間が経過すると電場は再び(b)のようになり、図には示していませんが、適当な質量のイオンはCとDの間に進むことができます。一方、重いイオンはBの方向に徐々に移動していき、電極Bが負の時に捕集されてしまいます。ただし、A−B間にある重いイオンは必ずBに捕集されるのでは無く、最初に鞍に置かれた位置によってはAに捕集されます。少し説明が長くなりましたが、適当な質量のイオンは電場の波に上手く乗ることができるのに対し、重いイオンは転げ落ち、軽いイオンは勢い余って飛び出してしまうと考えればよいでしょう。
以上の説明は、電極の軸方向を z とした場合の x-y 面でのイオンの運動です。イオンはイオン源で z 方向に加速されますので、x−y面ではこのような運動をしながらも全体としてはz方向(コレクタ側)に移動します。そして、特定の質量(質量電荷比)を持つイオンのみが、電極に捕集されずにコレクタに到達することになります。四重極型の特徴は、イオンの選別は z方向の速度に無関係であることです。つまり、イオン源からのイオンの速さは揃っていなくても構いません。また、磁場を必要としないことから、分析部が小型であることも特徴です。例えば写真1に示した分析管は、径が70のコンフラットフランジに接続するようになっています。しかも残留ガス分析には充分な分解能(注5)を持ち、重い分子の分析まで可能です。
このような特徴から、磁場偏向型分析計やオメガトロンに替わって、四重極質量分析計が広く用いられるようになり、現在では残留ガス分析計、あるいは分圧計の代名詞になっています。
マススペクトル
全圧計は圧力を表示するだけですが、分圧計では質量電荷比に対応するイオン電流を増幅した値を表示し、圧力に換算しないのが普通です(注6)。例えば質量電荷比が28の分子が窒素しか無い場合には、28に対応するイオン電流と窒素の感度から計算した分圧を表示することができます。しかし、実際には感度が窒素と異なる一酸化炭素も含まれていることが多く、窒素によるイオン電流と一酸化炭素によるイオン電流を分離しないと分圧を求めることができないからです。
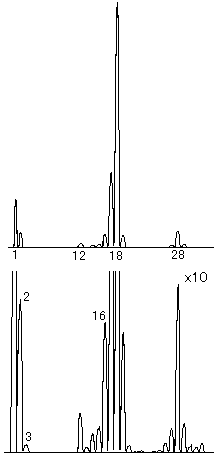 自作した赤外線真空加熱炉を排気した場合の残留ガススペクトル(右図)を例に説明しましょう。横軸は質量電荷比で、1から32まで走査しています。ほとんどのイオンの価数は1でしょうから、横軸は質量と考えても構いません。縦軸はイオン電流で、下図は上図の10倍の増幅率で測定したものです。
自作した赤外線真空加熱炉を排気した場合の残留ガススペクトル(右図)を例に説明しましょう。横軸は質量電荷比で、1から32まで走査しています。ほとんどのイオンの価数は1でしょうから、横軸は質量と考えても構いません。縦軸はイオン電流で、下図は上図の10倍の増幅率で測定したものです。
最も高いピークは、水(H2O: m=18) です。これは空気に含まれていた水分では無く、真空配管などの内壁に吸着されていた水分子です。その隣の m=17 と m=16 にもピークがありますが、それぞれ、OH と O に対応しています。これらはイオン源で水分子が分解することによって生成されます。安定ではありませんが、真空中でどこにも衝突しなければそのままの形で存在しています。用いた質量分析計の取扱説明書によると、水が分解して生成した OH と O のピークの高さは、H2O を 100 とするとそれぞれ 33 と 5 になるそうです。このスペクトルもほぼこのような比になっており、16〜18 のピークは水に起因すると言えます。
質量分析計ではこのように、1つの分子に相当するピークが複数にわたることがよくあります。最も高いピーク(主ピーク)を 100 として、他のピークの高さを相対的に表した値はパターン係数と呼ばれ、スペクトルから分子の種類を決定するための重要な指標です。パターン係数は分析管固有の値ですから、具体的な値については取扱説明書を参照して下さい(注7)。
m=16 に対応する O は、漏れた空気中の酸素分子が解離したものかもしれませんが、m=32 (O2) のピークが極めて小さいことから、可能性は少ないでしょう。また、メタン (CH4) の質量も 16 ですが、パターン係数によれば、もしメタンがあれば m=15 (CH3) にも同程度の高さのピークが現れる筈ですので、メタンもほとんど存在しないと思われます。このようにパターン係数が判っていれば、分子の有無を推定することができます。水では主ピークが m=18 にありますが、エチルアルコール(分子量46)では m=31 にあります。対応する解離片は CH2OH だと思われますが、この例のように、主ピークが分子量以外の質量に現れることがありますので、注意が必要です。
水以外に高いピークは m=1 と 28 にあります。m=1 は H であり、主に水の分解によるものと思われます。隣の m=2 は H2 です。また、下図を見ると m=3 にも僅かなピークがありますが、HD です。重水素ガス雰囲気で試料を加熱したことがありますので、その折りにどこかに吸着していたものでしょう。同様に、m=19 は HDO と思われます。一方、m=28 は前述したように N2 と CO の2種類が考えられます。大気中には CO はほとんど存在しませんが、真空中ではイオン源のフィラメント上で生成され易いそうです。N2 が分解した N (m=14) と CO が分解した C (m=12) のそれぞれのピークから N2 と CO の信号比を求めることは可能ですが、この図では m=12 にも m=14 にも他の分子に起因するピークが寄与していると考えられるため、これ以上の判定は困難です。
このように、分圧を求めることは一般に容易ではありません。 しかし、マススペクトルを見ると、どのような素性の真空かを知る手がかりは多く得られます。例えば油分があれば 40 近辺や 60 以上の部分に様々なピークが現れますし、空気の漏れがあれば 28(窒素)や 32(酸素) のピークが相対的に高くなります。また、例えば水素など特定の気体の分圧を測定することも可能です。
四重極質量分析計の性能
電離真空計と同じような熱陰極があるため、作動圧力は 10 mPa 以下です。できれば 1 mPa 以下で使用した方がよいでしょう。質量測定範囲はメーカーや機種によりますが、最小は1で最大は 100 〜 300 程度です。通常の残留ガス分析では m=100 までで充分でしょうが、高分子などの有機物やクラスター分子を検出する場合、最大質量は当然大きい方が便利です。ピーク間の分離能(△M)は、0.5 より小さければ十分で、たいていの(おそらく全部の)機種は満たしています。分解能で表現すると、M/△M>2M となります。
測定分圧の最小値、つまり検出限界は、コレクタの種類によって大きく異なります。ファラデーカップをコレクタとし、イオン電流を増幅するという、電離真空計のコレクタと同じような形式では、0.1〜1 nPa (窒素ガス) 程度ですが、二次電子増倍器という検出器を用いると 0.01 nPa 程度までの分圧を検知することができるそうです。前者はイオンをそのまま電流として測定するのに対し、後者はイオンが電極に衝突した際に発生する二次電子を、何度も増倍(数を増やすこと)することによって電流を増幅します。後者の方が感度が優れていますが、やや高価であることと、電極の汚れなどによって感度が変化することが難点です。 0.1 nPa 以下の分圧を測定する必要が無い限り、通常のファラデーカップ式の方が使いやすいでしょう。
接続方法
四重極型の場合、分析管は20cm程度の直管ですから、コンフラットフランジで接続するようになっています。写真1に示した例では分析管の重量は 2kg ですが、この他に高周波発振部などを直結するため、全体としては約 5kg になっています。従って、細い配管に水平方向に取付ける場合には、支持する必要があります。
(注1) 他の質量電荷比に対応する信号等から窒素と一酸化炭素の存在比を推定することは可能である。また、非常に分解能の良い質量分析計ではお互いを分離することは可能かも知れないが、残留ガス分析に日常的に用いられることは無い。 (注2) これは加速電圧 V を一定に保つだけでは達成されない。エネルギーはイオンが生成した位置における空間電位に依存するからである。 (注3) 重力の場合 F = mg (gは重力加速度)で、電場では F = qE (Eは電場の強さ)である。 (注4) 電極に印加される電圧は直流成分と交流成分があるため、この表現は直流成分から見た相対的なものである。 (注5) 質量Mのイオンに対して、分離可能な質量差を△Mとしたときの M/△M を分解能と言う。四重極型では△MはMに依存せず一定であるため、分解能は分析可能な質量に比例して大きくなるという、ちょっと奇妙なことになる。この定義は△MがMに依存する磁場偏向型やオメガトロンに由来しているのではないかと思う。 (注6) 最近、スペクトルを簡単に解析して分圧を表示する分圧計が市販されるようになった。 (注7) いくら固有の値といっても、どの分析管も数10eVの電子で電離・解離させているので著しく変わることは無い。真空の教科書には典型的なパターン係数が記載されているので、これを参考にしてもよいであろう。ある教科書によると水に対する OH の係数は 21 である。これは文中の値(33) と大きくは違わないが、一致しているとも言えない。つまり、一般的なパターン係数を用いる場合には、あまり細かい解析はしない方がよい。
以上
このページは、高木郁二が担当している京都大学工学部物理工学科の講義・実験を補う資料として作成したものです。ご意見・お問い合わせはこちらまでお願いします。