「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊
1−4 真空装置の構成
1998.09.12
keywords: vacuum system, rotary pump, diffusion pump, turbo
molecular pump
一般的な真空装置(真空系)の例をいくつか紹介します。真空を利用した装置は多種多様ですが、基本的な構成を知っておけば、初めて使う装置であっても、操作に戸惑うことは少なくなるでしょうし、自分で装置を組み立てる場合の参考にもなると思います。ここではおおよその事しか説明しませんので、材料や形状などにつきましては目次から辿ってご覧下さい。
最も単純な場合
図Aは最も単純な構成です。真空とは周囲の圧力よりも低い状態ですから、気密な容器の中に作らなければなりません。この容器は真空容器や真空槽などと呼ばれます。真空槽をそのまま放っておいても中の圧力は下がりませんから、真空槽内の気体(最初は空気)を排出するものも必要です。これを真空ポンプと言います。従って、真空槽と真空ポンプの組み合わせである図Aが最も単純な例ということになり、吸引濾過器が相当します。なお、JISでは真空ポンプは図のように表現します。通常、ポンプと真空槽の間は管で接続しますが、簡単のため、線で表しました。
RPを用いた例
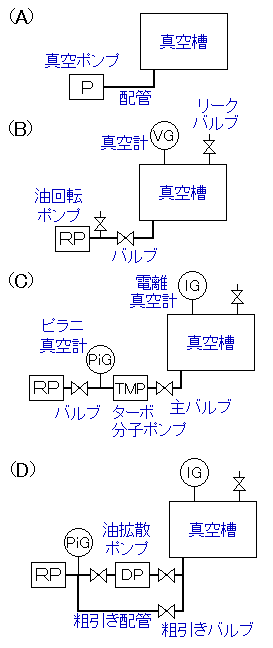 図Bでは、真空ポンプにRP(油回転ポンプ)を用いた例を示しました。到達した圧力を知るために真空計VGを真空槽に取り付け、ポンプを停止しても真空槽内を気密に保つために、配管中にバルブを設けています。真空槽の蓋は大気圧との差圧で吸い付きますので、蓋を開ける際にはリークバルブを通して中に空気を入れなければなりません(図Aでは配管を外すしかありません)。また、油の逆流を防止するために、RPは停止したら吸気側を大気に開放する必要がありますので、吸気側付近にもリークバルブがあると便利です。この構成に該当するのは、例えば真空乾燥器です(注1)。
図Bでは、真空ポンプにRP(油回転ポンプ)を用いた例を示しました。到達した圧力を知るために真空計VGを真空槽に取り付け、ポンプを停止しても真空槽内を気密に保つために、配管中にバルブを設けています。真空槽の蓋は大気圧との差圧で吸い付きますので、蓋を開ける際にはリークバルブを通して中に空気を入れなければなりません(図Aでは配管を外すしかありません)。また、油の逆流を防止するために、RPは停止したら吸気側を大気に開放する必要がありますので、吸気側付近にもリークバルブがあると便利です。この構成に該当するのは、例えば真空乾燥器です(注1)。
TMPを用いた例
10μPa 程度までの高真空を達成する場合の構成例を図Cに示します。TMP(ターボ分子ポンプ)は大気圧から作動させることはできませんので、RPとの2段構えになっている点が図Bと異なります。この図の例ではTMPを停止した状態で、先ずRPで
10 Pa 程度まで排気し(ピラニ真空計 PiG で確認します)、RPを運転したままTMPを起動します。真空槽内の圧力は、高真空領域で作動する
IG(電離真空計)で測定します。
注意点が2つあります。真空槽を頻繁に開閉するような場合には、次の図Dに示すような構成(DPの位置にTMPを置いた構成)にした方がよいことが1つです。もう1つは、例えば主バルブは高真空用のものでなければならないのに対し、RP側のバルブは中真空用でも構わないなど、同じ記号であっても、材料や部品が圧力領域に応じて異なることです。なお、RP側のリークバルブは省略しています(注2)。例えば、加速器のビーム輸送管にこのような構成が見られます。
DPを用いた例
DP(油拡散ポンプ)を用いた構成例を図Dに示します。圧力範囲は、10 mPa 〜 10 μPa 程度の高真空領域です。図Cと異なるのは、粗引きのための配管が追加されていることで、DPは大気圧から作動させることができないことと、一旦起動すると停止するまでに時間がかかることがその理由です。詳しくは別のページで説明する予定です。
DPは構造が単純であるにも拘わらず高真空まで排気できることから、図Dに示した構成はよく見かけます。TEMやSEMなどの電子顕微鏡、加速器の加速管やビーム輸送管、真空蒸着装置、イオンプレーティング装置、真空炉などです。ただ、必ずしもこれらの装置が図Dのようになっているとは限りませんし、最近ではDPの替わりにTMPが用いられることが多くなっています。
(注1) 実際には真空槽とポンプとの間に吸着剤があるし、バルブや真空計の位置も異なっている。基本的な構成が同じという意味である。 (注2) 逆流防止弁が備わっており、停止しても大気に開放しなくてよいRPの場合には、このような構成になる。



このページは、高木郁二が担当している京都大学工学部物理工学科の講義・実験を補う資料として作成したものです。ご意見・お問い合わせはこちらまでお願いします。
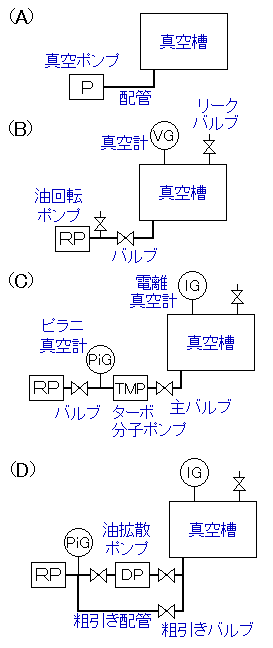 図Bでは、真空ポンプにRP(油回転ポンプ)を用いた例を示しました。到達した圧力を知るために真空計VGを真空槽に取り付け、ポンプを停止しても真空槽内を気密に保つために、配管中にバルブを設けています。真空槽の蓋は大気圧との差圧で吸い付きますので、蓋を開ける際にはリークバルブを通して中に空気を入れなければなりません(図Aでは配管を外すしかありません)。また、油の逆流を防止するために、RPは停止したら吸気側を大気に開放する必要がありますので、吸気側付近にもリークバルブがあると便利です。この構成に該当するのは、例えば真空乾燥器です(注1)。
図Bでは、真空ポンプにRP(油回転ポンプ)を用いた例を示しました。到達した圧力を知るために真空計VGを真空槽に取り付け、ポンプを停止しても真空槽内を気密に保つために、配管中にバルブを設けています。真空槽の蓋は大気圧との差圧で吸い付きますので、蓋を開ける際にはリークバルブを通して中に空気を入れなければなりません(図Aでは配管を外すしかありません)。また、油の逆流を防止するために、RPは停止したら吸気側を大気に開放する必要がありますので、吸気側付近にもリークバルブがあると便利です。この構成に該当するのは、例えば真空乾燥器です(注1)。