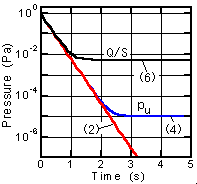 そこで、真空ポンプそのものに到達可能な圧力下限値 pu
が存在することを考慮し、(1)式を次のように書き換えます。
そこで、真空ポンプそのものに到達可能な圧力下限値 pu
が存在することを考慮し、(1)式を次のように書き換えます。「エネルギー理工学設計演習・実験2」別冊
1999.04.09
keywords: pumping speed, vacuum system, outgassing, pump-down time, time of evacuation
概要
真空槽を排気する場合に、所定の圧力まで到達するのに要する時間を排気時間、真空槽内の圧力変化を表した図を排気曲線と呼ぶことにします。ここでは、いくつかの仮定に基づいて計算した排気曲線の例を示し、排気時間ついて考察します。
最も単純な排気曲線
容積が V の真空槽を排気速度 S のポンプで排気した場合の圧力の変化を考えてみます。簡単のため、S は一定とします。微小な時間Δt の間に排気される気体の容積は SΔt ですが、この気体の圧力を p とすると、気体の量(圧力×容積)は SpΔt になります。一方、Δt の間に減少する圧力を −Δp とすると、真空槽内から排出された気体の量は −VΔp です。両者が等しいことから、
VΔp = −SpΔt (1)
となり、これを初期条件(時刻0での気体の圧力) p = p0 の下で解くと、
p = p0exp(-St/V) (2)
を得ます。つまり、系内の圧力は時間と共に指数関数的に減少することになります。
計算例1(粘性流領域)
以下の例では、共通して、内径 20cm、高さ 20cm のステンレス鋼製真空槽を想定します。真空槽の容積 V は 6.3 L ですが、簡単のため V = 6.0 L とし、同様に真空槽の内表面積 A は 0.2 m2 とします。この真空槽には排気速度 120 L/min (2 L/s) の粗引きポンプと、実効排気速度 30 L/s の主ポンプが接続されており、大気圧から 1 Pa までは粗引きポンプで、1 Pa 以降は主ポンプで排気すると考えます。
実効排気速度の項で述べたように、粗引き系では配管の粘性流コンダクタンスはポンプの排気速度よりもかなり大きく、実効排気速度と排気速度はあまり違いません(注1)。すると(2)式をそのまま適用することができ、S/V = 0.33 1/s、p0 = 100 kPa (大気圧) より、p = 1 Pa となるまでの時間 t は 35 s になります。
t = 35 s という数字は、実際に排気した時の経験に照らすと、桁が異なるほどでは無いにしても、少し短いようです。その原因の一つとして、コンダクタンスの低下が考えられます。粘性流ではコンダクタンスは圧力に比例するため、排気が進行すると実効排気速度が小さくなるからです。円形導管のコンダクタンスの項で示したように、コンダクタンスは分子流の場合に最も小さい値になり、半径が 1.25cm、長さが 100cm の導管を仮定すると、C = 2.0 L/s となります。これはポンプの排気速度と同じ値です。また、中間流領域を無視すると、粘性流と分子流の境界(円形導管のコンダクタンスの項(15)式) は 3.6 Pa です。これらのことから、数10 Pa 以下では実効排気速度は S よりも幾分小さくなると思われます。
例えば、100 kPa 〜 100 Pa での S を 2 L/s、100 Pa 〜 1 Pa での S を 1 L/s と考えると、t = 48 s になり、経験値に近くなりますが、これでもまだ短いようです。もう一つの原因としては、後に述べるガス放出があります。しかし、排気開始直後のガス放出速度はほとんど実測されておらず、これについて検討することは困難です。
いろいろと書きましたが、粗引きの場合には(2)式で計算した値の2〜3倍程度[1]であると思って概算する方がよいでしょう。
計算例2(分子流領域)
粗引きから主排気に切り替えた時刻を 0 とすると、このときの圧力 p0 は前述したように 1 Pa です。実効排気速度が(2)式中の S に相当することから、S/V = 5 1/s より、1 s 後の圧力は 6.7 mPa (1/150) に、3 s 後には 0.3 μPa (1/33万!) に達することになります。 実際に経験した人なら判ると思いますが、これほど早く排気されることはありません。
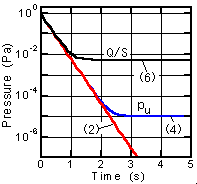 そこで、真空ポンプそのものに到達可能な圧力下限値 pu
が存在することを考慮し、(1)式を次のように書き換えます。
そこで、真空ポンプそのものに到達可能な圧力下限値 pu
が存在することを考慮し、(1)式を次のように書き換えます。
V(dp/dt) = −S(p - pu) (3)
(3)式の解は、
p = p0exp(-St/V) + pu[1 - exp(-St/V)] (4)
です。pu = 0.01 mPa (2インチ油拡散ポンプの代表的な数値)として、(2)式による排気曲線(赤線)と(4)式による排気曲線(青線)を比較すると、右図のようになります。 pu を考慮することによって、非現実的な圧力まで排気されることはありませんが、それでもなお、排気後 2 s で 0.1 mPa 以下まで達しており、実際の値とは相当食い違っているように思えます。
ガス放出も考慮した場合
固体には多量の気体が吸着されており、真空槽を排気すると内壁表面から気体(ガス)が放出されます。ガス放出量は一般には無視できないくらい多いため、特に分子流領域では考慮しなければなりません。単位時間当たりに放出されるガスの量を Q とすると、Q は流量と同じ次元なので、(3)式の右辺に Q を追加します。
V(dp/dt) = −S(p - pu) + Q (5)
Q を定数として(5)式を定数変化法などで解くと、次の解を得ます。(4)式と比較すると、ポンプの到達真空度 pu に Q/S が加わった形をしており、系の到達圧力が Q/S だけ増加することが判ります。
p = p0exp(-St/V) + (Q/S + pu)[1 - exp(-St/V)] (6)
後で述べるように、排気曲線を推定する場合に(6)式を用いることはほとんどありません。ただ、ガス放出量が重要であることと、初期には急激に圧力が減少する、つまり速やかに定常に達することを次の計算例で示すために導きました。
計算例3
Q の値を予測することは非常に困難ですが、Q は経験的に時間に反比例して減少すること[1]と、ステンレス鋼素材における1時間経過後の実測値(ガス放出速度) q = 0.020 PaL/m2s[3] から、以下のように見積もることにします。
先ず、主排気に切り替えるまでの排気時間を 0.025 時間 (= 90 s) とします。この数字は計算例1で求めた時間のほぼ3倍に当たります。次に、ガス放出速度は時間に反比例し、実測値を 90 s まで外挿できるものと仮定すると、q = 0.8 PaL/m2s となります。Q = Aq より、Q = 0.16 PaL/s です。従って、Q/S = 5.3 mPa を得ます。
この値を(6)式に代入して求めた排気曲線を、右上図中の黒線に示します。Q/S >> pu であることから予想されるように、圧力は最初は急激に下がった後ゆるやかに低下し、一定値(5.3 mPa) に達しています。この排気曲線は実際に近いように思われますが、確認することは困難です(注2)。
長時間排気する場合
(2)、(4)、(6)式に再三登場する exp(-St/V) 項は、圧力が時間と共に指数関数的に減少することを意味しています。計算例では S/V = 5 1/s なので、その逆数である時定数(注3)は 0.2 s です。つまり、右上図にも示されているように、系の圧力は 0.2 s 毎に 1/e ( = 0.368) に減少していき、速やかに定常状態に到達します。例えば、計算例3では 1 s 程度で定常値(Q/S)にかなり近くなっています。一方、ガス放出量は時間に反比例しますので、主排気開始(粗引き時間90 s 経過)直後 1 s 間のガス放出量の変化は 1% 程度です。Q は時間に依存するにも拘わらず、定数とおいて導いた(6)式を用いることができるのは、対象とする時間内(系が定常になる時間)では、ガス放出量がほとんど変わらないためです。
この考え方を延長すると、ガス放出量が変わるような長い時間を対象とする場合には、系はいつも定常状態になっていると言えます。つまり、(5)式において左辺は 0 となり、
p = Q/S + pu (7)
を得ます。(7)式では p は時間に依存しないように見えますが、Q に時間依存性(反比例の関係)があります。
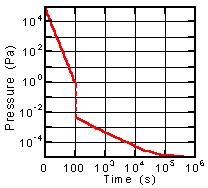 計算例4(最終版)
計算例4(最終版)
以上の検討をまとめると、排気曲線は右図のようになります。計算例3では主排気に切り替えるまでの時間を 90 s としましたが、図を見やすくするため、 100 s にしました。時間軸は、粗引きの間(0 〜 100 s)が線形で、主排気(100 s 以降)では対数であることに注意して下さい。
(i)粗引きでは(2)式を適用します。ただし、所定の圧力までの排気時間は(2)式で求めた値の2〜3倍を見積りまする。右図では 100 s で 1 Pa となるような S の値(0.69 L/s) を設定しました。 (ii)主排気に切り替えた直後は(6)式を適用します。ただし、全排気時間に較べると、(6)式が適用できる範囲はかなり狭く、右図の破線が示すように、圧力軸に平行になってしまいます。つまり、全体の排気曲線を描く場合には(6)式は必要ではありません。 (iii)主排気中は(7)式を適用します。ここでは Q が時間に反比例すると仮定し、計算例3の数値を用いました。20000 s 付近から傾きが -1 より小さくなっているのは、(7)式中の pu ( = 0.01 mPa) に圧力が近づいているためです。
この図から判るように、低真空〜中真空までは短時間で排気できますが、高真空になると、非常に時間がかかります。圧力は時間に反比例して減少するため、圧力を1桁下げるためには、時間が10倍必要になるからです。この例では、0.1 mPa を得るのに 80分かかることになり、まだ現実的ですが、1 μPa という超高真空(当然 pu はもっと低い値を仮定している)を得るためには 130時間も必要なことになります。このように長時間が経過すると、Q は時間の平方根に反比例する[1]ようになるので、実際には更に時間がかかるでしょう。ただし、適切な表面処理やベーキング(加熱によるガス放出の促進)を施すことによって Q を減らすことができますので、超高真空を得るためにはこのような処理が不可欠です。
(注1) 大気圧から排気すると暫くの間は乱流になるが、この場合も排気速度Sで排気されると仮定する。 (注2) ピラニ真空計の測定下限値はせいぜい 0.1 Pa なので、全域を測定することはできない。また、通常の電離真空計は 0.1 Pa 以下でしか使用することができず、しかもフィラメントを点灯して暫くは正確な値を表示しない。シュルツ計ならかろうじて確認することができるかもしれない。 (注3) 時定数という用語は電気回路のRC回路やLR回路の減衰時間として用いられるが、ここでは広義に解釈し、もとの 1/e に減少する時間という意味で用いている。
以上
このページは、高木郁二が担当している京都大学工学部物理工学科の講義・実験を補う資料として作成したものです。ご意見・お問い合わせはこちらまでお願いします。