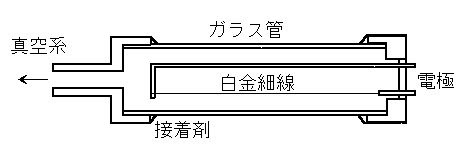
1998.06.30 I.Takagi 1998.08.04 rev.1 1998.09.01 rev.2
�@�w�������i�G�l���M�[���H�w�v�E���K�Q�F�d�q�r�[���j�ł́A�s���j�^��v�̌����Ɠ�����w�K���邽�߂ɁA���삵�������H�Ƒ���q���g�p���Ă��܂��i�s�̂̑���q�����p���Ă��܂��j�B���̃y�[�W�͂����̐���Ɋւ���o���ł��B�e�L�X�g�ɂ͊ȒP�Ȏ��������L�ڂ��Ă��܂���̂ŁA�����̂���l�͂��̃y�[�W�������Ċw�K���ĉ������B
�P�D�\���ƌ��� �Q�D���͂ւ̊��Z �R�D����q�̎d�l �S�D������H �T�D�s�̑���q�̎��� �U�D���͑���͈� �V�D���쑪��q�̎��� �@�ӎ� �@�Q�l����
�@�ቷ�̋C�̕��q�������̌ő̂ɏՓ˂���ƁA�ő̂���M��D���B�D�����M�ʂ��爳�͂����߂鈳�͌v�̈���s���j�^��v�ł���A����q�Ƒ���킨��т��������ԃP�[�u������\�������B������ɂ��Ă���ɏq�ׂ邪�A�C���[�W������������������Ղ��ł��낤����A���삵������q�̊T�O�}�������B
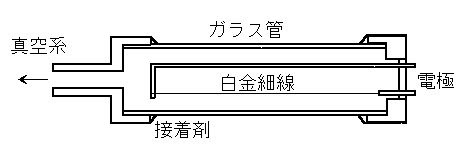
���ɊȒP�ȍ\���ł��邱�Ƃ�����ł��낤�B�������₷���悤�ɃK���X���g�p���Ă��邱�ƂƁA�G�|�L�V�n�ڒ��܂ŃV�[�����Ă��邱�Ɠ��������ẮA�s�̕i�Ɠ����\���ł���B�Q�̓d�ɂɓd���������A�����א������M���Ďg�p����B
�@���q���̈�ł́A�C�̕��q���Փ˂ɂ���Čő́i�����א��j����D���M�ʂ́A���q�̏Փ˕p�x�A�܂舳�͂ɔ�Ⴕ�A���̎��ŕ\�����B
��� = ����(�s�|�s0)��������������������� (1)
������ �� �͒P�ʖʐρA�P�ʎ��ԓ�����ɋC�̕��q���D���M�ʁi�M�����Ƃ����j�A�s �͌ő́i�����א��j�̉��x�A�s0 �͎��͂̋C�̉��x�i�K���X�Ǖlj��x�A�܂莺���ƍl���Ă悢�j�A�� �͋C�̂̈��́A�� �����R���q�M�`�����ł���B�� �͓K���W���ƌĂ�A�ȉ��̎��ŕ\�����悤�ɁA�ő̂ɏՓ˂������q�����ς��Čő̂̉��x�ɂǂ̒��x�܂ŋ߂Â��Ă��璵�˕Ԃ邩�������W���ł���B
��� = (�sg�|�s0)/(�s�|�s0)�������������� (2)
�����ɁA�sg �͌ő̂ɏՓ˂�����̋C�̕��q�̉��x�ł���B �sg ���ő̂̉��x �s �ɓ�������A�C�̕��q�͍ł������悭�ő̂���M��D�����ƂɂȂ�A�� = 1 �ł���B���̒l�͌ő̂̍ގ���C�̂̎�ނɈˑ�����B
�@�s���j�^��q�̍������́A�}�Ɏ������悤�ɁA�����א�(�t�B�������g)�ł���B��(1)�ɂ����āA�������̉��x T �����ɕۂ����Ƃ���Ɓi���͂̉��x �s0 �͈��ł���Ƃ��āj�A�M���� �� �� ���� �� �͔�Ⴗ��B�]���āA�� �� �� �����m�ł���A�� �𑪒肷�邱�Ƃɂ���� �� ������B���ꂪ�A�艷�x�^�s���j�^��v�̌����ł���B
�@���M���ꂽ�����א����瓦����M�ʂ� �p �Ƃ���ƁAQ �͑O�q�����C�̕��q���D���M�� Qg �A���[�h�����̐ڐG������ő̔M�`���ɂ���ē�����M�� Qs ������t�˔M�ɂ����M�� Qr �̘a�ł���BQg, Qs, Qr ��P�ʎ��ԓ�����Ɉړ�����M�ʂƍl����ƁA���ꂼ��A�ȉ��̎��ŕ\�����B
��pg = ��������(�s�|�s0)������������ (3) ��ps = �r��(�s�|�s0)/�k��������������� (4) ��pr = �����Ѓ�(�s4�|�s04)����������� (5)
��(3)�͎�(1)�̗��ӂɍא��̕\�ʐς��悶�����̂ł���A�� �� �� �͂��ꂼ��א��̒��a�ƒ����ł���B��(4)�͒���Ԃ̌ő̔M�`����\���Ă���AS �͍א��̒f�ʐ�(=��2/4)�A�� �͌ő̂̔M�`�����A�k �͑�\�����ł���B��(5)���̃ЂƃẤA���ꂼ��X�e�t�@���E�{���c�}���萔�ƌő̂��t�˗��ł���(*)�B
(*) ��(4)�ɂ����� L �̒�`�͂����܂��ł��邵�A��(5)�͖�����Ԃɑ��Ă��t�˕��M���ł��邩��A�����̎�����ő̓`���M���t�˔M�𐳊m�ɋ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ł́A���x �s �����̏ꍇ�ɂ͌ő̓`���M���t�˔M�����ɂȂ邱�Ƃ����̌`����������邽�߂ɗp�����B
�@����AQ �͔����א��̔��M�ʂɓ���������A�א��ɗ����d���� I�A�א��̒�R�l�� R �Ƃ���ƁA���̎������藧�B
��p = �pg �{ �ps �{ �pr = �h2�q������� (6)
�@�����ŁA�s �� �s0 �����ł���Ƃ���Ɓi���ꂪ�艷�x�^�s���j�̑O��ł���j�A��(4)�Ǝ�(5)��肻�ꂼ�� Qs �� Qr �͒萔�ƂȂ邱�Ƃ�����B���҂̘a���ȓd���l �h0 �Œu��������ƁA��(6)�͎��̂悤�ɏ�����������B
��h2 R = �`�� �{ I02 R���������������� (7)
�� �` = ��������(�s�|�s0)����������� (8)
I0 �́A���͂� 0 �̏ꍇ�ɍא��ɗ����d���A�܂�ő̔M�`�����t�˂ɂ���ē�����M�ʂ��������邽�߂̓d����\���Ă���B�܂��AA �͎�(3)���疾�炩�Ȃ悤�ɁAQg �ɂ����Ĉ��͂Ɉˑ����Ȃ������܂Ƃ߂��萔�ł���B�א��̒�R R�A�Ód�� I0(*)�A�萔 A �����m�ł���A�א��ɗ����d�� I ���玮(7)��p���Ĉ��� �� �����߂邱�Ƃ��ł���B I0 �͑���q�̌`���ގ��Ɉˑ�����萔�ł��邪�AA �͋C�̂̎�ނɂ��ˑ�����B
(*) �{���͌��d���ʂ�R�d�ɂ��d���̂��Ƃ������̂ŁA���̗p�@�͓K�łȂ���������Ȃ��B
�@�Ȃ��A���R���q�M�`�����́A
��� = (��+1)/2(��-1)�(��/2�l�s')1/2��� (9)
�ŗ^������[3]�B�� �̓{���c�}���萔�A�� �� M �͂��ꂼ��C�̂̔�M��Ǝ��ʁA�s'�͋C�̂̕��ω��x (T�{T0)/2 �ł���B��Ƃ��āA�s0 = 298K�AT = 473K�AM = 4.7E-26kg(N2�K�X)�A�� = 1.4(�Q���q���q)�@��������ƁA�� = 1.0 m/Ks �ƂȂ�B
�@�`�А��̃s���j�^��v����q�́A�戵�������ɂ��Ɣ����א��̒��a�� 25��m �ŁA�g�p���x�� 473K (200�C) �ł���B�����̉�H������ƃu���b�W�i�𗬁H�j�̔t�d�����牷�x�ω������o���A�I�y�A���v�ɍ������͂��čא��ɉ�����d���𐧌䂵�Ă���悤�ł���B����q�̓d�ɂ͂V���邪�A���ۂɂ͂Q�ɂ����g�p���Ă��Ȃ��B�܂�A����P�[�u���̓d���~���͕⏞���Ă��Ȃ��B���̂��߂��P�[�u�����͉ςł͖����Œ�ł���B����q�����Ď�������ƍא��̒����� 56mm �ł������B473K �ł̔����̒�R�� 1.76E-7��m �����R�l���v�Z����� 20�� �ł���B
�@��L�̎s�̕i���Q�l�Ɏ��삷�鑪��q�iPI38�ƌĂԁj�̎d�l�����߂��B�S������ł����Ă��\��Ȃ����A���a25��m�̔����א�������ł��Ȃ������̂ŁA30��m �̂��̂��g�p���邱�Ƃɂ����B�g�p���x�� 473K�A���̎��̒�R�l�� 20�� �Ƃ���ƁA��L�̒�R���ƒ��a���璷�������肳���B
�@����q�Ƃ��Ă̎d�l�͂���Ō��܂邪�A������v����ɂ͋�������d���i���邢�͓d���j�����ς����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��(7)�Ǝ�(8)�ɂ����āAI0 = 0�A�� = 1 �Ɖ��肵�Ap = 500Pa(*)�AT0 = 298K �̏ꍇ�̕��M�ʂ����߂�� 0.66W �ł���B�܂��A���̂Ƃ��̓d���Ɠd���� 180mA�A3.7V �ł���B
(*) ����\�Ȉ��͔͈͂ɂ��Ă͌�q����B
�@�@�\�P�@�s���j����q�̎�d�l
| ����q | �`�А��s�̕i | ����(PI38) |
| ��R�l R | 20�� | 20�� |
| �א��ގ��Ǝg�p���x T | �����A200�C | �����A200�C |
| �א����a d �ƒ��� a | 25��m�A56mm | 30��m�A80mm |
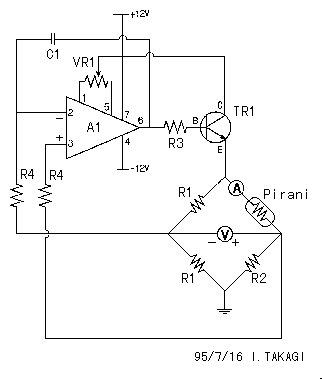
�@�s�̂̑����͈Ód�����l��������ň��͂Ɋ��Z���ĕ\������悤�ɂȂ��Ă��邪�A���삷�鑪���́A�א��̉��x�����ɕۂ��A�א��ɗ����d����\������@�\�݂̂Ƃ���B���x�����ɕۂɂ́A�����̒�R�������x�Ƌ��ɒP���ɑ������鐫���𗘗p����B�܂�A�E�̉�H�}�Ɏ����悤�Ƀu���b�W��H�ɂ���Ē�R�l�����ɕۂ悤�ɐ��䂷��B
�@��R R1 �� 1k��(1/2W,1%)�AR2 �͔����א��Ɠ�����R�l�� 20��(2W,1%)�ł���B�����̒�R�ƍא����u���b�W�ƂȂ��Ă���A�t�d�����I�y�A���v A1(LF356)�ɍ������͂��A�o�͂��p���[�g�����W�X�^ TR1(2SD856A)�̃G�~�b�^�t�H�����ŎāA�u���b�W�ɉ�����d��������A�P���ȃt�B�[�h�o�b�N��H�ł���B
�@�t�d���̓f�W�^���d���v(���v���� AP101-12-3, ����\1mV, max2V)�ŁA�א��ɗ����d���̓f�W�^���d���v(���v���� AP101-25-3, ����\1mA, max2A) �ő���E�\�����Ă���B�A�i���O���̃��[�^�ł��\��Ȃ����A�ŋ߂ł͗��҂̉��i���͂قƂ�ǖ����B�Ȃ��A�d���v�̓t�B�[�h�o�b�N��H������ɓ����Ă��邱�Ƃ��m�F���邽�߂̂��̂Ȃ̂ŁA�����Ă��\��Ȃ��B
�@�R�D�ł̌�������A�א��ɉ�����d���̏����3.7V ���x�ł��邱�Ƃ��킩���Ă���B�u���b�W�S�̂Ƃ��Ă͂��̂Q�{��7.4V ���v��B����̓I�y�A���v�ɕK�v�ȓd��(12V)�������������߁A�I�y�A���v�p�̓d���Ƌ��L���邱�Ƃ��ł���B�I�y�A���v���̂��͓̂d�����قƂ�Ǐ���Ȃ��̂ŁA+12V �̗e�ʂ� 200 mA ����Ηǂ��B���̑��A�f�W�^�����[�^�̋쓮�p�� 5V (1��� 80 mA) ���K�v�ł��邽�߁A+12V (300mA)�A-12V (100mA)�A5V (1A) �̃X�C�b�`���O���M�����[�^(KMC-15)���w�������B
�@���̑��̑f�q�̃p�����[�^�́AC1 (0.01��F)�AVR1 (30k��-B)�AR3 (300�� 1/8W)�AR4 (10k�� 1/8W) �ł���B�I�y�A���v�͕��ʂ̂��̂ł悭�AFET �^�� LF356 �͏���������������������Ȃ��B�h���C�o�̃g�����W�X�^ 2SD856A (80V-3A)�͎莝���̂��̂𗬗p�����B30 �` 100V �� 1 �` 3A �̃p���[�g�����W�X�^�Ȃ牽�ł��悢�ł��낤�B�u���b�W�Ɏg�p�����R�͂ł��邾�������ł��邱�Ƃ��]�܂����B�����ł͓��肵�Ղ��e��(�덷1%�j���g�p�����B�܂��A���M�ɂ���R�l�̕ω����ł��邾�����Ȃ����邽�߁AR2 �͗e�ʂ̑傫�����̂��]�܂����B
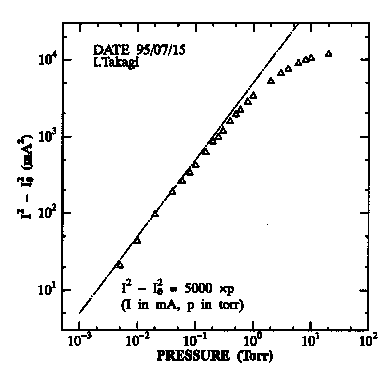
�@���삵�������̓�����m�F���A�s�̑���q�̓����ׂ邽�߁A�^�Ɏs�̑���q���Q�{�����t���A���ꂼ��s�̂̑����ƂT�D�Ő��삵�������ɔz�������B�^�̓��[�^���[�|���v�i���^��ł͖��g�U�|���v�p�j�Ŕr�C���A��o���u����Ĉ��͂𑪒肵����ɍĂю�o���u���J���Ĕr�C���鑀����J��Ԃ����B
�@���삵�������̔t�d���͏�� 1mV �ȉ��ɕۂ���Ă���A�d���̈��萫�� 1mA �ȓ��ł��������Ƃ���A����ɓ��삵�Ă�����̎v����B
�@���͂� 1mTorr(�`0.1Pa)�ȉ��̍��^��ł́A�א��̓d���l�͏�� 10mA ���������B����� I0 �ɑ������A�d�͂Ɋ��Z����� 2mW �ł���B�� = 0.2�̏ꍇ���t�˔M�ʂ���(5)���狁�߂�� 2mW �ƂȂ邱�Ƃ���A�ő̓`���ɂ����M�ʂ��t�˔M�ʂɊr�ׂď[���������Ɖ��肷��A���̌��ʂ͑Ó��ƌ�����B
�@��(7)�ɏ]���� I0 = 10mA �Ƃ��āAI2 - I02 �̒l���A�s�̑����̕\���l�i���́j�ɑ��ăv���b�g�������ʂ��E�}�Ɏ����B0.2Torr ���x�܂ł͗ǍD�Ȓ��������������Ƃ��킩��B�����̌X�����A
�I2 = 5000p + 100 (I;mA p;Torr)��������� (9)
�Ƃ���������������ꂽ�B����A�c���K�X�͒��f�K�X�ł���A�� = 1 �ł���Ɖ��肷��ƁA��(8)���AA = 5100 mA2/Torr (3.8E-5 A2/Pa) ��B���̒l�͏�̎������̌W�� 5000 �ɋ߂��A�قڗ��_�ʂ�̐��\�������Ă���ƌ�����B�������̌W���Ƃ̍��ق́A�� = 1 �Ɖ��肵�����Ƃ�A�c���K�X���ɐ������܂܂�Ă������Ɠ��ɋN������ƍl������B
�@�T�D�̎����l�ɂ��ƁA�s�̑���q�� I0 �� 10mA �ł������B�Ⴆ�� I = 11mA �Ƃ���ƁA��(9)��� p = 4mTorr (0.5Pa) �ƂȂ�B����ȉ��̈��͂̑���͂��̂悤�ȊȒP�ȃs���j�^��v�ł͍���ł���(*)�A�t�˕��M�ʂ�����\�Ȉ��͂̉����l�����肵�Ă���B����A�T�D�Ɏ������}�ɂ��ƁA������(9)�����藧�̂͂������� 0.2Torr (30Pa) �܂łł���A����ȏ�̈��͂ł͒������炩�Ȃ肸��Ă��܂��B����́A���͂������Ȃ�ƕ��q���ł͂Ȃ��Ȃ�A��(1)�����藧���Ȃ����߂ł���B0.2Torr �̒��f�K�X���q�����ώ��R�s���� 250��m �Ɛ����a��10�{�ł���A��ʂɌ����Ă��镪�q���̏����i��\������10�{�j�ɓ��Ă͂܂��Ă���B�Ȃ��A��������̂�������Ėڐ���t����A�s�̂̑����̂悤�� 20Torr �܂ő��肷�邱�Ƃ͉\�ł���B����ɍ������͂ɂȂ�ƁA���M�ʂ����͂ɂ�炸���ɂȂ��Ă��܂��A����s�\�ƂȂ�B
(*) ���^���ԂŔ����א��������K���X���p���A�t�˔M��ő̓`���M�A���邢�̓P�[�u���̓d���~����⏞�����s���j�^��v�ł́A�P���ȏ�Ⴂ���͂𑪒肷�邱�Ƃ��ł���B
�@��������Ƃ����f�[�^�𖢂�����Ă��Ȃ����߁A����f�ڂ���\��ł���B
�@�����̉�H�v�ɏ��������������@�V�b�����Ƒ���q�̕��i�삵�Ă����������������T���ɂ��̏����Ă���\���グ�܂��B
[1] ���������w�u���S�u�^��Z�p�v�A�ю�ŕҏW�A�����o�� (1985)340-345. [2]�u�^��Z�p�n���h�u�b�N�v�����O�ҏW�A�����H�ƐV���� (1990)306-314. [3]�u�^��Z�p�v�x�z����A������w�o�ʼn� (1983)21.
�ȏ�
���̃y�[�W�́A���؈�����S�����Ă��鋞�s��w�H�w�������H�w�Ȃ̍u�`�E������₤�����Ƃ��č쐬�������̂ł��B���ӌ��E���₢���킹���������܂ł��肢���܂��B